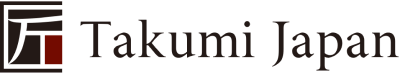人形/こけしとは
鑑賞用や遊び道具であるとともに、無病息災や子供の健やかな成長、五穀豊穣などへの思いが込められたもの。衣装を身に着けた人形や、木材を人型に加工し、頭部や胴体に絵柄を描いたこけしなどがある。

人形の歴史
CRAFT HISTORY

古くは、土を固めて焼いた土偶や埴輪などが作られていた。やがて宮中行事などに用いられる藁や紙の人型人形へ、そして貴族の女の子が「ひいな遊び」をする紙の人形へと変遷し、江戸時代には、桃の節句を祝う雛人形や、当時の人気歌舞伎役者を模したのがきっかけと言われる市松人形(日本人形)など、衣装を身につけた人形が作られるようになり、庶民へと普及していった。

現代の人形
MODERN CRAFT

近代になり豪華さを増していった雛人形は、住宅事情や時代の変化に伴い、現代はシンプルなものや小ぶりなものが主流になっている。

伝統工芸品指定の人形
CRAFT LIST

岩槻人形
江戸節句人形
江戸押絵
駿河雛具
駿河雛人形
名古屋節句飾
京人形

こけしの歴史
CRAFT HISTORY

764年、鎮護国家(仏教によって国を守る思想)を祈念するため、当時の天皇が木地師(木工職人)に作らせた、経を納める百万基の小塔が、こけしの起源と言われている。現在に伝わるこけしは、江戸時代に東北地方の温泉地で土産物として作られたのが始まり。当時から現代に至るまで、鑑賞用、愛玩用として親しまれている。

現代のこけし
MODERN CRAFT

従来の伝統こけしのほか、顔立ちや胴体のデザインを現代風にアレンジしたり、キャラクターをかたどったりした創作こけしと呼ばれるものも増えている。

伝統工芸品指定のこけし
CRAFT LIST

宮城伝統こけし